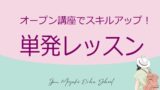「身体の動きをシンプルにする」
言葉では簡単そうですが、難しいと感じる方は少なくないでしょう。生まれてから今日に至るまでに刻まれた ”身体と思考の癖” が、誰にでもあるからです。
癖は、”自分を形成する一部” と言えますから、そこを問題視する必要はありません。むしろ不可欠な表現要素です。目的は二胡の上達ですよね。ですから、唯一無二の「自分という土壌」で、シンプルな身体を目指していきましょう。
実際に動きを観ながらでないとお伝えするのは難しいのですが、二胡愛好家の皆さんにも、できるポイントがあります。
「足さない」という事です。
演奏する時の自分を、少し考えてみて下さい。
思考も、動きも、「足していく」傾向にありませんか?
「雑音が出てしまった!」「右手に力が入る」、「ピッチが外れた!」「左手に力が入る」、「もっと弓は大きく」「ビブラートを深く」、なんだか分からなくなると「松脂をぬる」など、内容はどうあれ、とにかく「何かを足し続けている」のではないでしょうか?
意識して動くことは良い側面もありますが、このポイントでは、まずは「何かを考えること」をやめましょう。頭に浮かぶことを流して下さい。「うわ~、弾きにくい」と思うかもしれませんね。いかに思考の領域が大きいか分かります。
それでいいですので、
次は、耳を澄ませて、自分の音を「感じて」みて下さい。聞いてはいけません。能動ではなく、受動にして下さい。両の耳を開放するような気分で、弦の音の海に浮かんでみて下さい。
ここで雑音を感じたら、汚れた糸玉から一本の光る糸を引き出すような気分で、ボーイングしてみて下さい。どうでしょう。雑音はとれたでしょうか。(ボーイングはまた別の問題ですので、先へ進みますね)
そして、弾きながら、自分の身体を上からスクリーニングするように、心の目で眺めてみて下さい。力が入っているところがサーモグラフで赤くなるような具合で、無駄に動いている部分が、見えてきませんか?
ここがベースです。
ここから「引いて」いきます。
究極に、楽(らく)といえるところまで、引いていきます。
上半身を持ち上げていないか、肩甲骨を持ち上げていないか、肩・腕を持ち上げていないか、手首に力が入っていないか、弓のストロークに無駄がないか、指の動きに無駄がないか、等々です。
順番にスポットを当てて、ひとつずつ「余分」を引いていきましょう。肩甲骨・肩を持ち上げていれば、下げればいいだけです。
一人でできることには限界があるかもしれませんが、それでも多少は分かると思うのです。
なぜなら、
引いても同じ音がでているのなら、引いたものは「無駄にかけていた力」だと、ここで気づくことができるからです。それらは不要です。
そして、あらためて、自分の二胡の響きを「感じて」みましょう。(受動ですよ)

もっと、もっと、もっと。
呼吸を鎮めて、遠く、遥かなところまで、耳を澄ませましょう。
朝の光に開く蓮のように、自分の音の研磨へと向かって下さい。
ここから先は、それぞれの、鍛錬です。
美しい音は、汚れがありません。
物理的に言えば、雑音がありません。周波に乱れがありません。
『もともとは美しい輝きであったのに、余分な動きで(もとが)見えなくしてしまった』と思って下さい。それを取り戻すために、究極の引き算を目指してて下さいね。
GOOD LUCK!
◆こちらの記事も参考になると思います。チェックして下さいね。
◆座り方も大切なポイントです。身体の自由を広げるような座り方をしましょう。
◆直接指導を受けたい方は、単発レッスン、全国出張レッスンがあります。
◆観葉植物でいっぱいのレッスン室です♪
皆さんの二胡ライフが、もっと楽しくなりますように♪