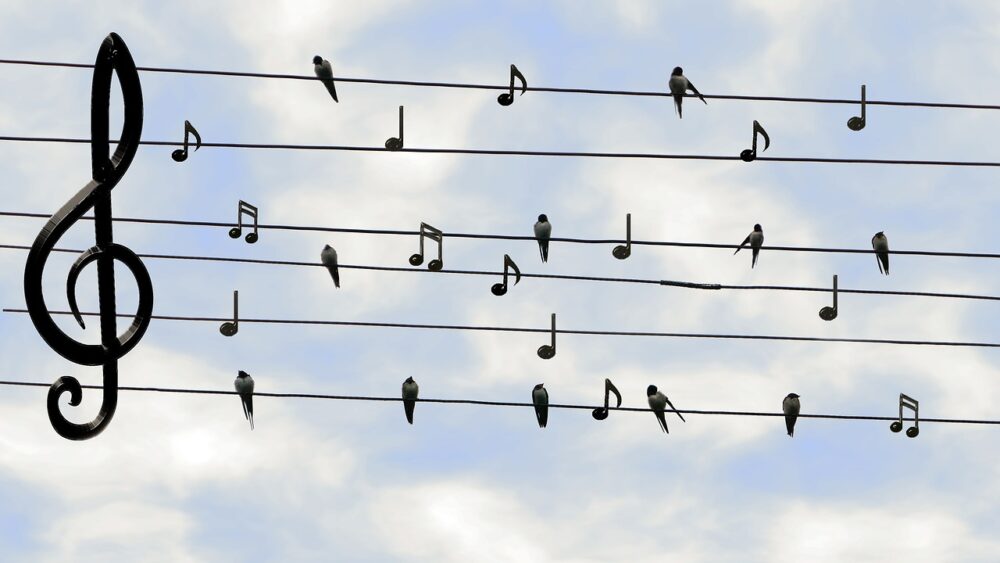はじめに
要点のみで、シンプルに説明していきます。多少の音楽用語は入りますが、理屈はできる限り端折ります。
五線譜から数字譜への書き換えは、深く考えると、首をかしげたままフリーズしてしまうと思います。丁寧に説明すると、よけいに訳が分からなくなりそうですので、「なあんだ、これでいいんだ!」と、ざっくり作業ができればという記事です。
数字譜はフランスのルソーが作ったものです。どうやら不評?だったようですが、音楽を心から愛するルソーらしく万民が理解しやすい簡易な移動ドの譜面を作りたかったようです。中国の記譜法ではありません。ということは、数字譜の原型は5線譜ですので、数字になっているとはいえ、内容は五線譜と同じです。このことからも簡単に書き換えができます。
・・・・・
最初にからくりをざっくり記します。
1:五線譜の「調」を調べる(調号で判断。分からなければ調号一覧で検索する。5秒で済みます)
2:調の主音を調べる(調名のアルファベット部分が主音。1秒で判断できます)
3:主音を数字譜の「1=ド」とする。(五線譜の調号にある#♭の全て!を完全無視していいので、五線譜の音符を単純に数字に置き換えていく。さくさくまいりましょう~。)
4:個々の音符に指示されている臨時記号の#♭を書き写す。(※ここのみ少し注意)
5:五線譜の音符の長さを、そっくりそのまま数字譜に書き入れる。(おたまじゃくしの8分音符は♪にょろんが1本なので1本線。16分音符♬は二重線なので2本線を入れる。)
6:最後に「1(ド)」の実音を決める。(「1=D」のアルファベット部分が実音)
おしまい!
五線譜の【調】の【主音】を、数字譜の【1:ド】とする

五線譜の調を調べよう!
①まずは調号をチェック
「調号」は、曲の「調」を示す記号です。
五線譜の左端に ”必ず” 記されていますので、最初にここをチェックします。
上の画像では、ト音記号のすぐ右隣に「♭が3つ」記されていますよね。これが「調号」です。
★「#」「♭」は各7個まで、「#♭なし」も調号を表します。
②調号一覧から「調」を調べる
「調号」でネット検索すると、「調号一覧表」がすぐに出てきます。
「調号=調名」が一覧表で出ていますので、まずは曲の「調名」を調べて下さい。
照らし合わせるだけなので簡単ですが、その際、以下の点に気をつけます。
※③「長調」で判断
ここで気づくのは、1つの調号(調名)には「長調」「短調」の2種類あるという事です。
★必ず「長調」で「調名」を調べて下さい。
*二胡の数字譜の書き換えにおいては、たとえ楽曲が短調でも「長調」を見ます。
※「長調:メジャーキー」しか書いていない一覧表もあります。(「短調」を書いていないだけです)
〈おまけ〉
※♭=短調ではありません。
【主音】を調べよう!
主音は、調の基準音です。

①長調の【主音】をチェック
【調】が分かると、ひと目で【主音】が分かります。超がつくほど簡単!です。1秒かかりません。
★前述の通り、短調ではなく【長調の主音】をチェックしましょう。
〈主音の見つけ方〉
調名にある「アルファベット」が【主音】です。
例えば、G dur(独):Gメジャー(英)でしたら、五線譜やピアノの「G = ソ」が【主音】です。
◆調名のアルファベットと【主音】
C=五線譜のド
D=五線譜のレ
E=五線譜のミ
F=五線譜のファ
G=五線譜のソ
A=五線譜のラ
B=五線譜のシ
〈補足〉
日本では、【調】は、イロハとアルファベットの2種類で表記されています。単純に言語の違いにすぎませんが、一瞬複雑に感じますよね。例えば『ニ長調(日本) : D dur(ドイツ語): Dメジャー(英語)』は、同じ調になります。
皆さんは普段からチューナーを使っていますから、昔言葉のイロハより、ABCの方が理解しやすいでしょう。
※イロハは覚える必要はありません。
※ここでは「音名」という言葉は、あえて使いません。
②【調号】→【主音】のカンタンな探し方
五線譜の調号「#」「♭」の場所から【主音】を探す方法もあります。「主音の見つけ方」で検索すれば解説サイトが色々出てきます。そちらを活用してもいいですね。
数字譜への書き換えがたまにしかないのなら、ここでご紹介している【調号一覧】→【長調】→【主音】を探すやり方が、てっとり早いかもしれません。
やりやすい方法でどうぞ。
【主音】を数字譜の【1/ド】に換えよう!

【主音】=数字譜の【ド/1】
ここまでの説明は、【五線譜の調号をチェック】するだけで、【長調の主音】がどれか分かるという内容でした。
★【主音】を【数字譜のド:1】とします → 数字譜の「ド」の位置が決まりました。
【ド:1】が決まれば、あとはこっちのものです。それに合わせて五線譜の音符を数字に書き直すだけです。サクサクと書き換えていきます。これにて終了!意外と簡単ですよね?
しかも、この作業。実は(何もしなくても)複雑な作業が済んでいるのです。
「音符」を「数字」に書き直す

ただ数字に替えるだけ!(想像以上に簡単!)
①全音・半音・調号の#♭は、計算にいれなくてOK!
数字譜に書き換える際、五線譜の『調号で指定されている#♭』と『ドレミファソラシの全音・半音』は、全て、計算に入れなくて大丈夫です! 完全に無視!してOKです。
数字譜の【ド:1】が決まれば、あとは『そのまま音符を数字に直していくだけ』の作業です。
「調号」の#♭は最大で7個まで五線譜につきますが、それらを全て無視できるんです。随分楽になりますよね。
②個々に指定された「#」「♭」「♮」のみ活かす
調号の「#♭」とは別で、特定の音符に指定された「#」「♭」「♮」のことを、臨時記号といいますが、★これのみ、数字譜にも記号をつけます。
臨時記号の扱い(大切)
①臨時記号の有効期間
皆さんご存知だと思いますが、一応記しておきます。
◆|臨時記号がつけられた音符~その小節の終わり|までが有効
◆|小節|をまたぐと、(その前についていた)臨時記号はリセットされる
◆|小節内の残りの音符|は、臨時記号は省略される。
※記譜上の親切で|小節内の残りの音符|にも、臨時記号がついている場合もあります。
②大切 ※「♮」の対応
★「♮」(ナチュラル)も忘れずに対処しますが、ひとつ気をつけることがあります。以下ABの内、Bの方に気をつけて下さい。
A : 個々の音符につけられた臨時記号「#」「♭」を戻すための「♮」の場合
→この「♮」は、そのまま数字譜に写します。
B : 調号で指定されている「#♭」の音符に「♮」がついた場合
→数字譜には調号がありません。ですから、この場合の「♮」をそのまま数字譜に記入すると、何をもとに戻すのか分からず、唐突につけられた「♮」が意味不明な記号になってしまいます。
★以下のように対応して下さい。
・五線譜の調号で#がついた音符に対する「♮」
→音符が(♮で戻るということは半音下がる)ので数字に「♭」をつける
・五線譜の調号で♭がついた音符に対する「♮」
→音符が(♮で戻るということは半音上がる)ので数字に「#」をつける
よほど複雑な曲でない限り、臨時記号は少ないです。
だからこそ、これらはフレーズのニュアンスを生み出す大切な表現になっています。臨時記号には作曲家の意図が込められていますので、見落とさずに数字譜に移しましょう。
③調号「#♭」の音符に、更に「#♭」がついている場合
これについては無視します。
数字譜には書き写さないで下さい。何も記入しません。
例えば、フレーズの中で「#♭」や「♮」が繰り返されて、どっちなのかひと目で判断しづらい時に、親切で記されている事があります。本来は省いていい記号ですが、こういう親切はわりとあります。
→五線譜の調号で#♭が指定されているのに、音符にも#♭がついてダブルになっている場合、重複してるだけですから、カットして考えて下さい。もとの音でいいです。数字譜には何も記しません。
※「#」がダブルで付く意味だと思って、音符を「2段階」で半音移動させる(全音上げる)という意味ではありません。
④分からないところは弾いて確認しましょう
分からなければ弾きながら処理をする方がいいです。机上だと??が増えるばかりですし、おそらく何箇所かは記譜ミスもありますので、途中でも最後でもいいですから、弾いて確認していきましょう。
オクターブ処理しよう!

上下の点をつける
次はオクターブを確定します。
【1:ド】より下は、数字の下に点。
オクターブ上は、上に点をつけていきます。
長さの下線・符点・スラーなどを書き込もう!
長さを表す下線や、符点、スラーなどを入れて仕上げます。
これらの説明は端折りますが、数字譜は五線譜がもとになっていますので、まるまる五線譜のそれを、数字譜に移して下さい。
※スラーに関して
ピアノのスラーは、弓で弾く擦弦楽器には難しい事があります。スラーの意図を汲みながら、適宜でつけましょう。
最適なキーを確定する

数字譜が完成した後で「キー」変更しよう!
演奏する【キー】は数字譜が完成してから決めます。
①最も弾きやすい「音階の位置」を決めよう!
ここまでの作業で数字譜は完成しました。
しかし、弾きにくい【キー】になっている場合もありますので、最後に、最適なキーに決めます。
数字譜はそのままでOKです。カラオケの「キー変更」と同じと思って下さい。ドの位置を変えて、曲のキーを丸ごとで上げたり下げたりして演奏してみましょう。
②実際に弾いてベストポジションを探そう
とりあえず数字譜を見て、どこでもいいですから弾きやすそうな位置で、一度演奏してみましょう。
実際に弾いてみると「ギリギリまで下の音域がいい」とか「外弦の開放弦を活かしたい」とか、「運指がしやすい」「高音がつらいから下げよう」など、ベストポジションがみえてきます。
★運指や音色から判断すると、最も快適な位置が決まるはずです。
それを最終的なキーとして決定しましょう。これで、二胡の学習法で言うところの、〈D調〉〈F調〉〈G調〉などが決まったということになります。
※注意〈D調〉〈F調〉〈G調〉は、調名ではない
※注意したいのは、〈D調〉〈F調〉〈G調〉などは「調名」ではないという事です。
調という文字が入っているので錯覚しますが、これらは数字譜の【1/ド】を基準音にした「音階の位置」を表すものです。
※確かに「調」に基づいてはいるのですが、これらには「長調」「短調」の区別がありません。また、「長調」と「短調」は、数字譜の【1:ド】の位置が同じであっても、別の調名になりますので、そのことからも調名と捉えない方が良いでしょう。
最後に【1= 】を記入する

最後ですよ!
実音を調べて【1= 】に記入しよう!
数字譜の【1:ド】の位置が決まったわけですから、その実音(音名)を、譜面の先頭に【1=「 」】として、アルファベットで記入します。実音はピアノの音と思ってOKです。
※分からなければ、数字譜と実音の対応表を見るか、チューナーで調べて下さい。

お疲れさまでした。
想像よりもシンプルに済んだのではないでしょうか?
数字譜変換ソフトなどもあるようですので、そういうものを使ってみるのも楽な方法かもしれません。
どうぞティタイムでブレイクして下さいね。
興味がある方は、こちらの記事も参考にどうぞ。
皆さんの二胡ライフがもっと楽しくなりますように♪